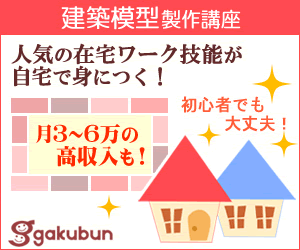「今年中に登録販売者の資格を取りたい!」と決意した、専業主婦の意味豆まみいです(*´∀`*)
前回の記事はこちら⬇︎
sikaku.imimame-mamii.net


今回は今現在の自分の実力を把握するため、事前にテキストで学習することなくいきなり過去問題を解いて見ることにしました。
ただ…全範囲の第1章から第5章までだと問題数も多く、子どもを見ながらまとまった時間をとるのは難しいので今回は2章まで(^_^;)
それでも真面目に勉強するのなんて大学以来なので、途中集中力が切れそうになって大変でした😂笑
使ったのはこちらのテキスト⬇️
第1章・第2章合わせて65問あり、解くのに大体1時間10分くらいかかりました💡

採点してみたら
⬇︎
⬇︎
⬇︎
⬇︎

第1章は25問中18点‼︎
な、なんとすでに7割以上正答してる!(◎_◎;)
登録販売者の試験では総出題数に対して7割程度、かつ5つの出題項目すべてで4割以上正答すれば合格できると言われているのでこれは楽勝かも🎵
と、調子にのりましたがすぐに撃沈(;_;)
第2章は40問中20点でした…
1章よりだいぶ正答率は下がりましたが、それでも一応5割はとれています(^_^;)
でも2章のところは問題を読んでも分からないところが多く、消去法や当てずっぽうで答えた問題もたくさんあったので、ただ単に運が良かっただけかもしれません😥
今回過去問を解いて2つの章について感じたことは
【第1章・医薬品に共通する特性と基本的な知識】は
- 薬についての一般常識的な問題(いわゆる概論)が多い
- 妊婦や小児が薬を使う時の配慮等、主婦にとって簡単すぎる問題が出る。
- 答えを知らなくても想像力で補って正答を導き出しやすい
- 暗記が必要なのは医薬品のリスク評価についての基準と、薬害訴訟の歴史についてくらい
よって、1章の項目については初めに1日程度勉強するくらいで十分な気がします💡ただ試験の受験者全員にとっても「点取り科目」となっているはずなので取りこぼしのないよう、この科目では8〜9割は正答できるようにしたいです。
医薬品のリスク評価とは
医薬品は食品より厳しい安全性基準が要求されており、そのリスク評価は4つに分類される。
GLP「 Good Laboratory Practice(グッド ラボラトリー プラクティス)」
医薬品の安全性に関する非臨床試験(動物実験)の基準。薬効薬理試験や一般薬理試験などがこのGLPに準拠して実施される。
GCP「Good Clinical Practice (グッド クリニカル プラクティス)」人を対象とした
臨床試験における医薬品の効果と安全性の国際的な基準
GPSP「Good Post-marketing Study Practice(グッド ポストマーケティング プラクティス)」医薬品の製造販売後の調査と試験の実施基準
GVP「Good vigilance Practice(グッド ヴィジランス プラクティス)」医薬品の製造販売後の安全管理基準。製造販売業者がいつ発生するか分からない副作用や品質不良を常時監視するための基準
全部「G」から始まり、「P」で終わるので非常にややこしいですね( ˊᵕˋ ;)💦
L→動物を使った
非臨床試験C→人を使った
臨床試験PS→販売後の調査と試験
V→販売後の安全管理(副作用や品質不良に対して)
私は真ん中の文字とキーワードをピックアップして覚えることにしました💡
※薬害訴訟については長くなるので、また次の機会にまとめたいと思います( ´ ꒳ ` )ノ
【第2章・人体の働きと医薬品】は
- 体の仕組みやそれに対する薬効に関する問題がほとんど
- 学生時代理科、生物が得意だった人は最初からある程度点数取れそう
- 消化器系、呼吸器系、循環器系、泌尿器系、外皮系、骨格系、神経系、末梢神経系、目、鼻、耳、歯、筋組織等一通りの人体の働きについて理解する必要がある。
- 医薬品の剤形(錠剤、シロップ、軟膏、クリーム)については1、2度読めば理解できる
- 副作用について色々な症状の名前があるのでそれを覚える必要あり
テキストでも2章の範囲は6日分の期間がもうけられているので、じっくり勉強していいと思います。人体の働きについては生活に直結している部分もあり、大人になってから学ぶとまた新たな発見がありおもしろそうです☆
第2章は文字だけで記憶・理解するのは難しいのでノートに図を描きながら覚えるしかないですかね💦
身体の各部の名称を4歳の息子に教えながら、器官の働きを子どもでも分かるように説明しアウトプットすることでより記憶に残るようにしたいと思います!